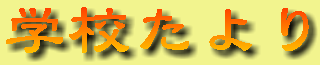| クズの種を集めて地球緑化に役立てる |
 |
 |
葛は、マメ科の植物で、日
本から中国、東南アジアに分
布し、日当たりのよい山野に
生育している半低木性のつる
性植物です。 |
| (写真提供:とんび岩さん) |
↑(精細写真12万2462バイトにリンク) |
| 相生小学校では、地球緑化に役立てようと1989年から全校でクズの種を集めています。 |
花は、写真で見るように、紅紫色で、「秋の七草」の一つです。
奈良県吉野郡の国栖(くず)地方が葛の語源と言われています。
吉野郡の国栖には、渡来人が住んでいました。彼らは、その地方に群生する蔓草を食用にしていました。また、彼らは、蔓草の繊維を使って衣服を作っていました。そのことから、蔓草を「くずかずら」・「くず」というようになったと伝えられています。
葛の根をカッコン(葛根)といい、漢方薬の葛根湯に使われます。また、葛の根を干して粉にしたものをクズコ(葛粉といい、高質の澱粉を含んでいるので、これを使ってクズモチ(葛餅)やクズキリ(葛切り)を作ります。
クズモチ(葛餅)は、水で溶いたクズコ(葛粉)に砂糖を加え、火にかけ透明感が出るまでよく練ります。練りあがったものを冷やして、砂糖入りきな粉や黒の蜂蜜などをかけて食べます。
クズキリ(葛切り)は、水で溶いたクズコ(葛粉)を火にかけ透明感が出るまでよく練ります。練りあがったものを冷やして、細長く切り、砂糖入りきな粉や黒の蜂蜜などをかけて食べます。 |
![]()
![]()
![]()