
| (17)六騎塚(ろっきづか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
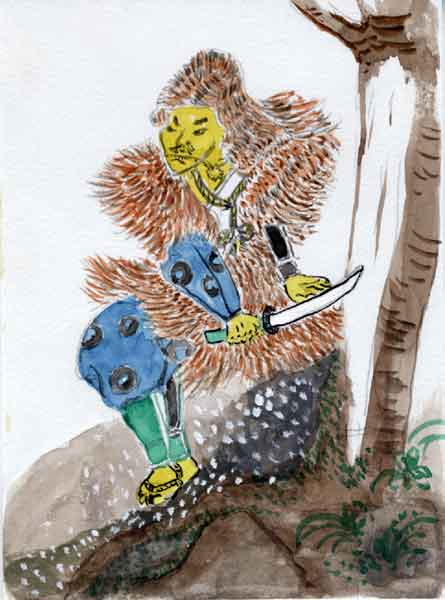 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『相生市史』第四巻には、「一九一八年(大正七)刊の『日本伝説叢書(そうしょ)播磨(はりま)の巻』に相生市にかかわる伝説五篇が載せられている」「一九七五年(昭和五十)十二月に刊行された玉岡松一郎の『播磨の伝説』の中に紹介された相生の伝説は・・相生市にかかわる”六騎塚(ろっきづか)”」「大阪読売新聞の姫路支局が・・『播磨伝説風土記』を・・一九七六年六月一冊の本として刊行したが、その中にも「六騎塚」の見出しで、相生市にかかわる伝説が載せられていて、そのいずれも『播磨鑑(かがみ)』以前にさかのぼって伝えられた伝承であることが知られる」とあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六騎塚とは、児島高徳の父範長主従の六人が自害した跡に建てられた墓のことです。 相生市にかかわる伝説として、色々な書物に取り上げられていながら、『相生市史』やその他の史資料、地元の伝承には、残念ながら、辿りつけませんでした。 そのような伝説が残っていなかったのか、何らかの理由で残さなかったのでしょうか。 今後の課題です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考資料1:それでは、藤澤衛彦編著の『日本傳説叢書<播磨の巻>』には六騎塚はどう扱われているのでしょうか。 延元元(1336)年5月、足利尊氏・直義が九州から攻め上った時、新田義貞の弟・脇屋義助は、足利直義に敗れて、播磨へ引き退きました。同じく、敗れた児島備後守範長とその子・高徳ら27騎は、脇屋義助の軍に合流しようと、坂越の浦にやって来ました。児島高徳は、ケガをしていたので、近所のお寺で休むことにし、その他は那波の浦をそっと進んで行きました。 播磨の守護・赤松円心の配下だった那波の城主宇彌(うや)三郎左衛門重氏は、50騎を率いて追いかけました。伊保庄(今の兵庫県高砂市伊保)で追い付き、そこから、阿彌陀宿(今の兵庫県高砂市阿彌陀町)までの間に、18回も戦ひを交えました。児島範長ら26騎はだいたい討れて、辻堂に駆け込んだ時には、範長ら6騎になっていました。今は最後と、主従6騎は、この辻堂で自害しました。 児島高徳は、坂越のお寺に留っていたので難を免れることができました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延元元(1336)年五月、足利尊氏が九州から攻め上った時、官軍は敗れて、脇屋義助は播磨へ引き退いた。同じ戦さに敗軍した児島備後守範長、子息備後三郎高徳は、残党の一族今木・大富・和田・松崎などを始めとして、二十七騎、義助の軍に合せんものと、三石の南の山路を、夜もすがら越して、坂越の浦へ出た時、高徳は、先の軍の疵のために、此辺の僧に寄り留まり、他は那波の浦手を忍んで落ちて行った。赤松の勢であった那波の城主宇彌(うや)三郎左衛門重氏は、早くも之を聞き付け、手勢五十騎ばかりを以て其跡を慕ひ、伊保庄(今の伊保村辺)でこれに追ひ付き、其處から、阿彌陀宿(今の阿彌陀村)までの間に、十八度も戦ひを交えた。二十七騎の者共は、大方討れて、とある辻堂のあるに駆け込んだ時には、範長主従僅か六騎に討なされてゐた。今は最後ぞと、主従は、此辻堂で腹かつ切つて自害したが高徳ばかりは、疵の為めに坂越に留つたので此難を免れ得た。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考資料2:玉岡松一郎編著の『播磨の伝説』には六騎塚はどう扱われているのでしょうか。 建武3(1336)年、備後三郎高徳は残党27騎で赤穂郡那波の浦手を落ちましたが、那波の城主・宇野三郎左衛門重氏が聞きつけ、50騎を率いて跡を追い、伊保の庄で追いつきました。27騎の者は大方討たれ、ただ六騎となり、今は逃れ難しと、阿弥陀の宿の辻堂に駈け込み腹を切って死にました。それが六騎塚です。 小島(原文のママ)高徳の墓は赤穂市坂越町妙見山にあります。 元禄の時(1688〜1704年)、妙見寺の住職・観了が百碑を見ると、正平20(1365)年5月13日と年号を刻んであったことが理由といいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六騎武者塚(姫路市別所町北宿) 建武三年(一三三六)備後三郎高徳は残党二十七騎で赤穂郡那波の浦手を落ちたが那波の城主・宇野三郎左衛門重氏が聞きつけ手勢五十騎ばかりで跡を追い伊保の庄で追いつき二十七騎の者は大方討たれ、ただ六騎となり今は逃れ難しと阿弥陀の宿の辻堂に駈け込み腹を切って死んだ、その塚である。 児島高徳墓(赤穂市坂越町妙見山) 小島三郎高徳の墓。元禄の時(一六八八−一七〇四)妙見寺の住僧・観了が百碑を見ると正平二十年(一三六五)五月十三日と年号を刻んであった故という。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考資料3:読売新聞姫路支局編著の『播磨伝説風土記』には六騎塚はどう扱われているのでしょうか。 『播磨伝説風土記』では、官軍方の新田義貞の弟・脇屋義助が敗れたのは、湊川の戦いで、軍を摂津から播磨に引き退いたとしています。児島備後守範長とその子・高徳ら27騎が脇屋義助と合流するため、「夜もすがら山越えをして赤穂郡坂越の浦へ出た」としています。高徳がケガをしていたので、「範長はやむなく知り合いの僧の元へ高徳を預け置いて他の手勢とともに先を急いだ」。 「ところが足利方についていた那波(現在の相生市)の城主宇弥三郎左衛門重氏がこれを聞きつけ、手勢五十騎を従えてそのあとを追った。伊保の庄(現在の高砂市)のあたりで児島範長の一行に追いつき、そこから阿弥陀宿(高砂市阿弥陀町)までの間に十八度も戦いを交えた。 児島方の武将たちは大方討たれて、ふと見かけた辻堂へかけ込んだときには範長主従はわずか六騎に減っていた。”今はこれまで”と主従はこの辻堂の中で腹かき切って果てた」。 この記述から、藤澤衛彦編著の『日本傳説叢書<播磨の巻>』を下敷きにしていることが分かります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考資料4:ここで上記史料の3点を検証します。 脇屋義助の軍を官軍と指定しています。赤松円心やその配下の宇彌三郎左衛門重氏らは賊軍となります。 相生の三郎左衛門重氏の姓が「宇彌」、「宇野」、「宇弥」だったりします。彌は弥の古字だとすると、「宇彌」と「宇野」が残ります。 高徳の姓が「児島」、「小島」だったりします。 脇屋義助の敗れた戦いを湊川の戦いとしたり、たんに敗れたりとか、同じ戦いに敗れたりとしています。 史資料分析の大まかさが目につきます。 そこで、児島高徳の時代背景をしっかり、おさらいする必要を感じました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考資料5:1332年から1336年までの歴史事実を検証しました。 1332(元徳4)年3月、後醍醐天皇は、流罪地の隠岐に向けて、京都を出発しました。 児島高徳は、後醍醐天皇を奪回しようと、播磨と備前の国境にある船坂山で、待ち受けていました。そのことを察した警護の佐々木道誉は姫路の西の今市から、山陽道を通らず、龍野・上郡を抜けて、美作の院庄に入りました。児島高徳はしかたなく、院庄にもぐりこみ、木の幹に「天莫空勾践時非無范蠡」(越王勾践は呉の捕虜になったが、范蠡の奇略により呉を滅ぼし、勾践を助けたという中国の故事)を書き連ねました。 11月、河内の悪党である楠木正成は、千早城で挙兵しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1333(正慶2)年1月19日、楠木正成が四天王寺で六波羅軍を攻撃しました。 1月21日、播磨の悪党である赤松円心は、反幕府の立場で播磨の苔縄城で挙兵しました。 2月、幕府軍が赤坂城を攻略しましたが、千早城では楠木正成が反撃しました。 閏2月24日、後醍醐天皇は、隠岐を脱出して、伯耆の海岸にたどり着きました。 閏2月28日、後醍醐天皇は、伯耆の船上山から討幕の綸旨を各地に発しました。 閏2月24日、赤松円心は、尼崎に進出して、幕府軍を撃破しました。 3月、足利高氏は、名越高家とともに幕府軍を率いて伯耆へ向かいました。近江の鏡宿に来た時、後醍醐天皇の綸旨を受け取り、高氏は、官軍として戦う決意をしました。 4月27日、足利高氏は、篠村八幡宮で「源氏の棟梁として朝敵北条氏を打倒する」と宣言しました。 5月7日、足利高氏は、赤松円心らと京都に突入して、六波羅探題を攻略しました。 5月9日、六波羅探題の北条仲時らは、番場で自刃し、光厳天皇らが捕えられました。 5月22日、新田義貞が鎌倉に侵入し、鎌倉幕府が滅亡しました。 1333(元弘3)年5月25日、後醍醐天皇は、光厳天皇を廃位し、年号を元弘に戻しました。 5月、後醍醐天皇は、姫路の書写山円教寺に入り、赤松円心と会見しました。 6月5日、後醍醐天皇は、京都に帰り、摂政・関白を廃止し、天皇親政を宣言しました。 6月、後醍醐天皇は、恩賞方を設置しました。 6月13日、護良親王が帰京し、征夷大将軍となりました。 8月5日、足利高氏・新田義貞らの論功行賞を行いました。高氏は、後醍醐天皇の尊治親王の一字を与えられ、足利尊氏と改名しました。 9月、後醍醐天皇は、記録所を再興し、窪所・雑訴決断所・武者所など設置しました。 10月、後醍醐天皇は陸奥将軍府を設置し、義良親王(5歳)を将軍として、北畠親房の子・顕家(15歳)に補佐させ、北畠親房を同行させました。 12月、後醍醐天皇は、鎌倉将軍府を設置しま、成良親王(7歳)を将軍として、足利尊氏の弟直義を補佐させました。 この頃、京都では、軍功第一の尊氏が新政権の要職につかない「尊氏なし」という噂が流れました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1334(建武元)年1月、後醍醐天皇は、大内裏造営を開始し、その費用は武士から徴収しました。 10月、後醍醐天皇は、武家社会の不変の法を無視して、旧領回復令を出しました。 11月、護良親王は、足利尊氏の動きに危険を察知して挙兵し、尊氏も兵を集めました。 11月、後醍醐天皇は、尊氏を敵に回すことを不利と考え、護良親王を鎌倉に送りました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1335(建武2)年7月22日、北条高時の子・時行は、武士の不満に支えられて、鎌倉を奪還しました。 7月23日、足利直義は、鎌倉を退く時、護良親王の殺害を命じました。 8月、足利尊氏は、勅許を待たすに、鎌倉に下向し、鎌倉を奪回しました。 9月、後醍醐天皇は、足利尊氏に上洛の命令を出しました。 11月18日、足利尊氏は、新田義貞の討伐を名目に挙兵して、後醍醐天皇に反旗を翻しました。 11月19日、後醍醐天皇は、足利尊氏追討の命令を出し、追討大将軍に新田義貞を任命しました。ここに、建武の新政が終わり、南北朝の動乱が始まります。 11月26日、悪党の赤松円心は、足利尊氏側について挙兵しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1336(建武3)年1月、後醍醐天皇は、楠木正成らの勧めで、比叡山の麓の東坂本へ動座しました。 1月10日、足利尊氏は、大軍を率いて、平穏に入洛し、京都を占領しました。 1月12日、京都に入った尊氏の大軍は食糧難に苦しみます。これが楠木正成の作戦でした。 2月、後醍醐天皇は、新田義貞に西征の勅命を出しましたが、義貞は寵姫の匂当の内侍との別れを惜しんで出陣が遅れました。 2月、足利尊氏は、その間に、丹波篠村から三草(兵庫県加東郡社町)を越えて、室津泊(揖保郡御津町)に辿り着きました。尊氏は、室津の見性寺で、「敗れた原因は朝敵にあり」という赤松円心の助言を受け入れました。 2月12日、足利尊氏は、持明院統の光厳上皇に院宣を要請して、海路九州へ敗走しました。 1336(延元元)年2月29日、後醍醐天皇は、京都に帰り、年号を延元(南朝)と改めました。 3月2日、院宣を手にした足利尊氏は、九州の多々良浜の戦いで勝利します。 3月、新田義貞は、播磨国鵤荘(揖保郡太子町)の楽々山(立岡山)で、赤松軍を撃破しました。 3月、新田義貞は、白旗城(赤穂郡上郡町)の赤松円心の抵抗で、身動きが取れなくなりました。 3月下旬、赤松円心は、足利尊氏に上洛を促す手紙を書きます。 4月3日、足利尊氏は、上洛の船出をしました。建武の新政に不満の50万の大軍が参集しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月5日、足利尊氏は、備後の鞆津に上陸しました。軍議をひらき、水陸二方面作戦を採用しました。 5月10日、足利尊氏は海路を進みました。足利直義は陸路を進みました。新田義貞は、京都に援軍を要請しました。 後醍醐天皇は、新田義貞からの使いにより、楠木正成に兵庫にいって、義貞と力を合わせて合戦せよと命じました。この時、正成は「尊氏を京都に引き入れ、兵糧攻めにすれば、朝敵を滅ぼすことができます」(「敵機に乗たる大勢に懸合て、尋常の如くに合戦を致候はゞ、御方決定打負候ぬと覚へ候なれば、新田殿をも只京都へ召候て、如前山門へ臨幸成候べし。…京都を攻て兵粮をつからかし候程ならば、敵は次第に疲て落下、…新田殿は山門より推寄られ、正成は搦手にて攻上候はゞ、朝敵を一戦に滅す事有ぬと覚候」)と必死で訴えました。 しかし、公卿の結論は、「戦う前に帝都を捨て、1年に2度も比叡山に臨幸することは、帝位を軽視するのに似ている。すぐに兵庫へ下るべし」(未戦を成ざる前に、帝都を捨て、一年の内に二度まで山門へ臨幸ならん事、且は帝位を軽ずるに似り…只時を替へず、楠罷下るべし)というものでした。 楠木正成は、「この上は何を言っても仕方がない」(「此上はさのみ異儀を申に及ばず」)と無念の言葉を飲み込みました。 5月16日、楠木正成は、3000騎の内700騎を連れて、京都を出ました。桜井(奈良県桜井市)で、嫡子楠木正行(11歳)に2300騎を付けて河内に返します。名場面「桜井の別れ」です。 5月18日、陸路の足利直義軍が迫ると、三石城(岡山県三石町)を占拠していた新田義貞の弟・脇屋義助は退いて義貞軍と合流しました。義貞・義助は白旗城の囲みを解いて兵庫に退きました。 5月19日、尊氏は室津に上陸し、見性寺で、赤松円心と会って今後の対応を話し合いました。 5月23日、足利尊氏は、室津で「よき順風」を待って、船出しました。 5月24日、新田義貞軍は、兵庫で、楠木正成軍と合流しました。 5月24日、足利尊氏の軍船は、播磨の大蔵谷(兵庫県明石市)の沖合いに停泊しました。 5月25日、正成軍は会下山一帯、義貞の弟・義助軍は経ケ島、義貞軍は和田岬に陣を布きました。 午前10時、細川定禅軍が後方かく乱戦術を取ると、義貞軍は、正成軍を見捨てて、弟義助と共に退路を断たれることを恐れて、京都へ逃げ帰りました。 5月25日午後5時、楠木正成軍は、16度の戦いで73騎になってしまいました。正成は、弟楠木正李に何か願い事はあるかと聞くと、正李は「七生まで只同じ人間に生まれて、朝敵を滅ぼさやとこそ存候」と答え、「兄弟共に差違え、同枕に臥にけり」(『太平記』)。 楠木正成の首は、京都の六条河原にさらされたが、足利尊氏は、白木の箱に入れ、丁重に、河内の遺族の元に送り返したといいます。 1336(建武3)年8月15日、後醍醐天皇が退位し、北朝の光明天皇が即位しました。その結果、南朝は空位時代がしばらく続きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考資料6:以下の表は、南北朝時代(1318年から1340年)の元号表です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南北朝時代(1318年〜1392年)までの元号表←クリック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考資料7:参考資料5と参考資料6を参照しながら六騎塚をさらに検証します。 新田義貞の弟・脇屋義助軍は戦いに敗れたのではなく、足利直義軍の接近に恐れをなして、三石城から兄・新田義貞がいた白旗城に逃げ落ち、その後、湊川に退いたことが分かります。そこで児島高徳父子は再起を期して、義貞・義助兄弟を頼って、湊川に行こうとしたことが分かります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考資料8:六騎塚伝説の源になっている『日本伝説叢書』は、大正7(1918)年の発行です。 明治42(1909)年、国定教科書では南北両朝が並立して書かれていました。 明治44(1911)年1月19日、読売新聞社説は「もし両朝の対立をしも許さば、国家の既に分裂したること、灼然火を賭るよりも明かに、天下の失態之より大なる莫かるべし」と主張し、南北朝正閏問題が発生しました。 2月4日、帝国議会は南朝を正統とし、国定教科書の執筆責任者・喜田貞吉は休職処分となりました。そして、三種の神器を所有していた南朝が正統であるとして、教科書を改訂しました。 つまり、足利尊氏などを天皇に叛いた逆賊・大悪人・賊軍、楠木正成・新田義貞・児島高徳などを天皇に殉じた忠臣・官軍とする風潮がありました。そして、『太平記』(1370年ころまでに成立)や『播磨鑑』(1762年ころまでに成立)などに基づいて、六騎塚は誕生したといえます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考資料9:大正時代から戦前の小学校では、児島高徳は教科書や小学校唱歌にも採用されました。 児島高徳 文部省唱歌 一 船坂山や杉坂と 御あと慕ひて院の庄 微衷をいかで聞えんと 桜の幹に十字の詩 『天勾践にうせん)を空しうする莫(なか)れ 時苑蠡(はんれい)無きにしも非(あら)ず』 二 御心ならぬいでましの 御袖露けき朝戸出に 誦じて笑ますかしこさよ 桜の幹の十字の詩 『天勾践を空しうする莫れ 時苑蠡無きにしも非ず』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考資料10:1923((大正12)年、六騎塚の碑は、そうした風潮の中で、兵庫県が建てました。 では、官軍・忠臣の代表である児島高徳の父ら27騎を追い詰めた相生の那波城主・宇彌三郎左衛門重氏はどんな扱いだったのでしょうか。多分、逆賊・大悪人・賊軍扱いだったことでしょう。 1392(明徳3)年、南朝・後亀山天皇が北朝・後小松天皇に三種の神器を譲渡し、南北朝が合体しました。これを元号により明徳の和談といいます。その後、北朝・後小松天皇の皇統が現在まで続きます。 北朝の系統を引いている江戸時代のお公家さんは、北朝正統論を支持しています。 明治天皇は、南北朝時代に限って南朝が正当性をもつと裁断されています。 現在の天皇も、当然、北朝・後小松天皇の皇統です。 現在、北朝の光厳天皇・光明天皇・崇光天皇は、皇位の象徴である三種の神器(鏡・剣・玉)を保有していたとされています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考資料11:後世、逆賊・大悪人・賊軍扱いだった相生の那波城主・宇彌三郎左衛門重氏は、当時どんな扱いだったのでしょうか。 楠木正成も赤松円心も悪党と言われます。悪党とは、鎌倉時代の体制には入れ切れない新しい実力者集団で、指導者からは扱い切れない「悪い奴」(悪党)と評されていたのです。 後醍醐天皇が新しい体制を作ろうとする動きをすると、敏感に反応しました。赤松円心則村は、播磨国赤松村の則村でした。しかし、実力で、播磨の支配者となりなした。伯耆を脱出して、なんなく播磨を通過して、後醍醐天皇が京都に無事帰えることが出来たのは、円心のお陰です。 しかし、なんなく播磨を通過した背景を理解せず、非常に困難な時に援助した側近を優遇した後醍醐天皇の建武の新政(公家の復興政治)に不満を持ったのは円心でした。円心らの心を察知した足利尊氏は、武士による新しい体制を樹立しようとしました。これに賛同した円心は、陰に陽に、尊氏を支援します。後醍醐天皇に冷遇された赤松円心は、足利尊氏によって播磨の守護に任命されます。さらには、室町幕府の重職・三管四職の四職の1人に赤松氏が山名氏らとととも就任しています その円心に共鳴したのが相生の那波城主・宇彌三郎左衛門重氏でした。当時、宇彌三郎左衛門重氏は、新しい時代をめざす人物としての扱いを受けていたと思われます。 私たちは、バランスを欠いた主義・主張にとらわれず、歴史的事実を冷静に分析し、伝説も正当に評価したいものです(文責:有政一昭)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挿絵:丸山末美 |
| 出展:『相生市史』第四巻・『郷土のあゆみ』 |