| NO.006 |
第一章古代国家の起源 |
|
| 凡例:[1 ](項目)、「2 」(人名)、『3 』(書籍名・作品名) |
|
| 2] |
農耕社会の発展 |
|
1 |
A[1 ]農耕-前期(北九州~伊勢湾)→中期(関東地方)→後期(東北地方) |
|
2 |
前期の水稲農業 |
|
|
イ |
低湿地を利用した*C[2 ]農耕(排水施設を必要とする水田→低生産性) |
|
|
ロ |
*C[3 ]農具(開田・耕作するための木製の耕具の総称) |
|
|
|
① |
A[4 ](柄と鍬とが80度の木製耕具) |
|
|
|
② |
B[5 ](スコップ形の木製耕具) |
|
|
|
③ |
A[6 ](低湿地の深田の中を歩く特大の下駄) |
|
|
|
④ |
その他ーE田舟、Eえぶり |
|
|
ハ |
播種-籾のD[7 ](苗代を用いず、直接水田に種子を播く方法) |
|
|
二 |
収穫-A[8 ](稲穂を積みとる石器)、A[9 ](その方法) |
|
|
ホ |
保管-D[10 ]穴(地下施設)、B[11 ]倉庫(高床施設) |
|
|
ヘ |
脱穀-B[12 ]、B[13 ] |
|
|
ト |
板付遺跡(井戸、貯蔵庫、湿田、直播)、唐古(鍬・鋤・杵・臼) |
|
3 |
中期の農業 |
|
|
イ |
滋賀大中湖南-潅漑用水路 |
|
|
ロ |
大阪池上-貯蔵庫、井戸、700本の石包丁 |
|
4 |
後期の農業 |
|
|
イ |
農業技術の発展-*A[14 ]工具(鉄で作られた工具の総称) |
|
|
|
① |
石庖丁→A[15 ]へ |
|
|
|
② |
磨製石斧→D[16 ]へ、刃先鉄製の鍬 |
|
|
|
③ |
D[17 ](深田に堆肥を踏込む道具) |
|
|
ロ |
広大なE沖積平野を水田化 |
|
|
|
① |
静岡-*A[18 ]遺跡(畔で区画された2000平方mの水田50枚、田下駄発見) |
|
|
|
② |
静岡-C[19 ]遺跡 |
|
|
|
③ |
奈良-B[20 ]遺跡(鍬・鋤・臼・杵)、B[21 ]遺跡(福岡) |
|
|
ハ |
西日本の一部-*C[22 ](地下水位が低く、潅漑施設が必要な水田)→ |
|
|
|
|
|
生活の舞台は丘陵・海辺の低地へ(湿田より高生産性) |
|
5 |
*A[23 ](弥生時代に始まった農耕)の普及→生活の変化 |
|
|
イ |
衣-木製のD[24 ](樹皮使用)と石製のD[25 ](紡ぎ道具) |
|
|
ロ |
食(用途に応じて発達した土器) |
|
|
|
① |
C[26 ](貯蔵用)、C[27 ](蒸し器) |
|
|
|
② |
C[28 ](煮炊き用)、B[29 ](盛付け用) |
|
|
ハ |
住-水田に近い低地(A[30 ]式住居) |
|
6 |
社会の変化(農産物の蓄積→階層の分化) |
|
|
イ |
首長の出現-数集落が治水・潅漑のため、共同作業・利害調整→水系単位 |
|
|
ロ |
A[31 ](統一国家が形成される過渡的段階の小国家の分立) |
|
|
|
① |
地域集団(首長)-闘争・併合→有力集団の首長(支配者としての性格を強化) |
|
|
|
② |
瀬戸内海沿岸・近畿地方の山頂・丘陵上の軍事的集落ー*C[32 ]性集落 |
|
|
|
③ |
九州~関東地方-*E[33 ]集落(濠で囲まれた小集落) |
|
7 |
墓制の変化 |
|
|
イ |
北九州 |
|
|
|
① |
共同墓地から*A[34 ]墓(甕に遺体を埋葬する墓) |
|
|
|
|
a |
副葬品-中国製の鏡(大陸との交通) |
|
|
|
|
b |
豊かな財宝をもつ特権的首長の出現 |
|
|
|
② |
B[35 ]墓(ドルメン)、*C[36 ]墓(偏平な石を組合わせた中に遺体を埋葬) |
|
|
ロ |
その他の地域 |
|
|
|
① |
木製のC[37 ]墓、壷製のD[38 ]墓 |
|
|
|
② |
地面に壙を穿って遺体を埋葬するD[39 ]墓(墓穴式) |
|
|
ハ |
特色 |
|
|
|
① |
共同墓地(山口土井ケ浜180体)→ |
|
|
|
|
|
*B[40 ]墓(四方の台状部の周囲を溝で囲む。九州~東日本)→ |
|
|
|
|
|
*墳丘墓(弥生後期西日本) |
|
|
|
② |
葬法-*D[41 ](死者の両脚を伸ばして埋葬する方法) |
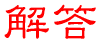 |
正解数( )問/問題数(41)問=正解率( )%
|