| NO.125 |
第6章 幕藩体制の確立(2) |
|
| 凡例:[1 ](項目)、「2 」(人名)、『3 』(書籍名・作品名) |
|
| 5] |
諸産業の発達 |
|
1 |
林業(都市の発達による建築資材の需要増大) |
|
|
イ |
幕府-木曾桧 |
|
|
ロ |
諸藩-秋田杉 |
|
2 |
漁業 |
|
|
イ |
漁法-*D[1 ](網を使う摂津・和泉・紀伊地方の漁法)の伝播 |
|
|
|
① |
上方漁民-関東・三陸・蝦夷・四国・九州へ進出 |
|
|
|
② |
C地曳網-鰯(九十九里浜)、D船引網、D定置網 |
|
|
|
③ |
捕鯨業-九州~土佐~紀伊 |
|
|
|
④ |
鰊・昆布漁-蝦夷地 |
|
|
ロ |
経営 |
|
|
|
① |
後進地域-E[2 ](漁業経営者)・E[3 ](零細漁民)制 |
|
|
|
② |
上方・関東-入会い漁業 |
|
|
ハ |
産物 |
|
|
|
① |
紀州熊野のC[4 ]→E鯨油 |
|
|
|
② |
蝦夷の昆布・鰊、江戸の海苔、土佐の鰹 |
|
|
ニ |
輸出-*A[5 ](俵に詰めた海産物。中国料理の材料としてBいりなま |
|
|
|
|
|
こ、B干あわび、Bふかのひれ)、昆布 |
|
3 |
製塩業-*C[6 ]式塩田(瀬戸内沿岸) |
|
|
イ |
潮の干満を利用して砂浜に海水を導入 |
|
|
ロ |
阿波撫養、播州赤穂、安芸竹原、讃岐坂出 |
|
4 |
鉱業 |
|
|
イ |
金 |
|
|
|
① |
佐渡のA[7 ]、伊豆のC[8
・ ]、E甲斐 |
|
|
|
② |
銀-但馬のA[9 ]、石見の[10 ]、E出羽の院内 |
|
|
|
③ |
銅 |
|
|
|
|
a |
伊予C[11 ](大坂の泉屋(住友)の経営) |
|
|
|
|
b |
C下野[12 ](幕府経営)、出羽の阿仁・尾去沢 |
|
|
|
|
c |
鉄-出雲砂鉄、陸中釜石 |
|
|
|
|
d |
その他-E石炭(筑豊)、E石油(越後) |
|
|
ロ |
17世紀後半-金・銀減少→銅増大 |
|
|
ハ |
露天堀→坑道堀、砂金→山金の精錬法へ |
|
5 |
手工業の発達 |
|
|
イ |
農村家内工業(農業と結び付いた自給自足の手工業) |
|
|
ロ |
都市の独立手工業 |
|
|
|
① |
各地に名産誕生-陶磁器、漆器、製紙、醸造業 |
|
|
|
② |
繊維工業の発達 |
|
|
|
③ |
薩摩の保護・専売政策→農村における商品生産の拡大 |
|
|
ハ |
18世紀 |
|
|
|
① |
問屋制家内工業 |
|
|
|
② |
資本を持つ問屋が農家に原料や道具を貸し与えて、製品を買い取る |
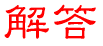 |
|
正解数( )問/問題数(12)問=正解率( )%
|