| NO.132 |
第6章 幕藩体制の確立(2) |
|
| 凡例:[1 ](項目)、「2 」(人名)、『3 』(書籍名・作品名) |
|
| 3] |
諸学問の発達 |
|
1 |
儒学の発達(合理的・現実的思考)→他の学問にも影響 |
|
2 |
歴史学-儒学者による古文書を引用した実証的な研究 |
|
|
イ |
官撰 |
|
|
|
① |
林羅山・鵞峰-『本朝通鑑』 |
|
|
|
② |
|
水戸藩のA『1 』(実証的で大義名分論を貫く。E彰考館で編集) |
|
|
ロ |
私撰 |
|
|
|
① |
|
A山鹿素行 |
|
|
|
|
a |
B『聖教要録』 |
|
|
|
|
b |
『武家事紀』(古文書を引用した新しい歴史研究) |
|
|
|
② |
A新井白石 |
|
|
|
|
a |
B『2 』(公家政権より武家政権への推移を段階的に区分) |
|
|
|
|
b |
C『3 』(『日本書紀』神代巻についての合理的解釈) |
|
|
|
|
c |
C『4 』(白石の自伝) |
|
|
|
|
d |
E『5 』(大名の事蹟) |
|
3 |
自然科学 |
|
|
イ |
*A[6 ]学 |
|
|
|
① |
薬の本になる草を意味し、植物・動物・鉱物の薬用効果について研究する学問 |
|
|
|
② |
博物学 |
|
|
|
③ |
*A「7 」-B『8 』(1362種の動・鉱・植物を解説) |
|
|
|
④ |
C「9 」(本草学大成者)-C『10 」(博物学的本草学の大著) |
|
|
|
⑤ |
E小野蘭山(幕府医学館の教授で、各地で薬草採集) |
|
|
ロ |
農学 |
|
|
|
① |
*A「11 」のA『12 』(見聞と体験に基づく農業技術) |
|
|
|
② |
その他-E田中丘隅E『民間省要』、E『清良記』、E『百姓伝記』 |
|
|
ハ |
*B[13 ](中国伝来の数学より発達した日本独自の数学) |
|
|
|
① |
D「14 」のD『15 』(数学算盤の普及。級数・根・体積・幾何) |
|
|
|
② |
*A「16 」 |
|
|
|
|
a |
和算の大成者。円周率・円弧の長さや円の面積を計算、筆算式代数学 |
|
|
|
|
b |
.C『発微算法』、E『括要算法』 |
|
|
|
③ |
E算盤、E天秤、E算額 |
|
|
ニ |
天文暦学 |
|
|
|
① |
*A「17 」(別名渋川春海)-*A[18 ] |
|
|
|
|
a |
平安以来の宣明暦の誤りを長期天体観測の結果修正。授時暦により1684年完成 |
|
|
|
|
b |
1年を365.2417日と計算 |
|
|
|
② |
太陰・太陽暦 |
|
|
|
|
a |
新月から次の新月の前日までを1か月とする |
|
|
|
|
b |
大の月(30日)、小の月(29日)を適当に配置 |
|
|
|
|
c |
太陽の運行に合せるため19年に7回の閏月をおく |
|
|
|
|
d |
気候と合わないので、農村では太陽の運行をもとにした二十四節気(立春・夏 |
|
|
|
|
|
至・秋分・冬至など)をめやすに農作業 |
|
|
|
③ |
干支-年月日・時刻・方角、陰陽道(吉凶をうらなうもの) |
|
|
ホ |
医学-名古屋玄医の古医法(元・明の説を否定し、臨床実験を重視) |
|
|
へ |
E碁所(ごどころ、囲碁界の最高位)-E本因坊、E井上家、E安井家、E林家 |
|
4 |
*A[19 ](日本の古典を研究し、民族精神の究明に務めた学問) |
|
|
イ |
*D「20 」-制の詞(使用禁止の詞)を否定。自由研究主張→E『梨本集』 |
|
|
ロ |
D下河辺長流-『万葉集』の注釈に新説。契沖を水戸光圀に推薦。『万葉集管見』 |
|
|
ハ |
*A「21 」 |
|
|
|
① |
多くの実例により茂睡の正しさを証明し、和歌を道徳的に解釈する従来の説を排斥 |
|
|
|
② |
②B『22 』(万葉集の注釈書) |
|
|
ニ |
*B「23 」 |
|
|
|
① |
『源氏物語』『枕草子』を研究。作者のありのままの意図を探求。国学発展の先駆 |
|
|
|
② |
C『24 』(源氏物語の研究)、C『25 』(枕草子の研究) |
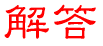 |
|
正解数( )問/問題数(25)問=正解率( )%
|