| NO.264 |
第9章 近代日本とアジア(2) |
|
| 凡例:[1 ](項目)、「2 」(人名)、『3 』(書籍名・作品名) |
|
| 8] |
戦争中の文化 |
|
1 |
思想 |
|
|
イ |
E[1 ]史観 |
|
|
ロ |
E[2 ]事件 |
|
|
|
|
|
1942年 |
E「3 」の「世界史の動向と日本」(『改造』)、発禁。著者検挙 |
|
|
|
|
|
1943年 |
『中央公論』『改造』廃刊 |
|
2 |
自然科学 |
|
|
イ |
E「4 」-E吉田肉腫、E癌研究所 |
|
|
ロ |
E「5 」-ビニロン |
|
3 |
文学 |
|
|
イ |
民俗学-E「6 」 |
|
|
ロ |
詩人-E「7 」、E宮柊二(しゅうじ) |
|
|
ハ |
評論 |
|
|
|
① |
E『日本浪漫派』刊行 |
|
|
|
|
a |
E「8 」-左翼から転向→日本回帰による近代の超克 |
|
|
|
|
b |
E「9 」-ロマンチシズムから日本主義・民族主義・日本ファシズムへ |
|
|
|
② |
E「10 」-プロレタリア文学への鋭い批判 |
|
|
|
③ |
E「11 」-心理主義と私小説を組み合わせた独自の世界を展開 |
|
|
ニ |
小説 |
|
|
|
① |
E[12 ]会(1942年)-会長徳富蘇峰(文学者を戦争協力に組織化) |
|
|
|
② |
E「13 」(都会人的感覚と転向問題)-E『如何なる星の下に』 |
|
|
|
③ |
E「14 」-主知的・抒情的なインテリ作家の独自の境地を保つ |
|
|
|
④ |
E「15 」-社会的リアリズムを根底に庶民の姿態と心情を描写 |
|
|
|
⑤ |
E「16 」-風俗的リアリズムの立場 |
|
|
|
⑥ |
E「17 」(近代的知性・抒情性の作品)-E『風立ちぬ』 |
|
|
|
⑦ |
D「18 」-D『麦と兵隊』 |
|
|
|
⑧ |
D「19 」 |
|
|
|
|
a |
社会性と平均的な市民的倫理観 |
|
|
|
|
b |
E『生きてゐる兵隊』(日本軍の残虐行為の描写で発禁) |
|
4 |
芸能 |
|
|
イ |
Eプロレタリア劇団-築地小劇場の分裂 |
|
|
ロ |
E軽演劇 |
|
|
|
① |
昭和初期-エロ・グロ・ナンセンス |
|
|
|
② |
浅草-エノケン。新宿-ム-ランル-ジュ |
|
|
ハ |
音楽 |
|
|
|
① |
E「20 」-E『東京音頭』 |
|
|
|
② |
E「21 」-E『影を慕いて』、E『酒は涙か溜息か』 |
|
5 |
美術 |
|
|
イ |
E日本美術報国会(1943年) |
|
|
ロ |
E大東亜戦争美術展(1942年) |
|
6 |
宗教 |
|
|
|
|
|
1930年 |
E創価教育学会→戦後再建(大石寺) |
|
|
|
|
|
1936年 |
Eひとのみち教団、不敬罪 |
|
|
|
|
|
1939年 |
E宗教団体法 |
|
|
|
|
|
1946年 |
ひとのみち教団、PL(パ-フェクト・リバラティ)として再建 |
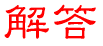 |
|
|
正解数( )問/問題数(21)問=正解率( )%
|