| NO.282 |
第10章 現代世界と日本 |
|
| 凡例:[1 ](項目)、「2 」(人名)、『3 』(書籍名・作品名) |
|
| 4] |
特需と経済復興 |
|
1 |
背景 |
|
|
イ |
1950年代の国際情勢の変化→日本の経済の復興に大きく影響 |
|
|
ロ |
経済安定計画によって不況下の日本経済→朝鮮戦争で息を吹き返す |
|
|
ハ |
A[1 ]条約による独立以後、日本経済の復興と発展 |
|
2 |
経過 |
|
|
|
|
|
1948年 |
E[2 ]資金(占領地域救済資金)などによる緊急輸入→食糧確保 |
|
|
|
|
|
1949年 |
経済安定計画→不況 |
|
|
|
|
|
1950年 |
A[3 ]戦争(朝鮮半島)勃発→不況下の日本経済の活性化 |
|
|
|
|
|
|
①アメリカ軍のD[4 ](特別需要)-1950~1953年間23億ドル |
|
|
|
|
|
|
a.アメリカは朝鮮戦争で必要な大量の軍需品・役務を日本に発注 |
|
|
|
|
|
|
b.この特需が国内生産を活発化 |
|
|
|
|
|
|
②*D[5 ]景気 |
|
|
|
|
|
|
a.繊維・金属を中心とする特別需要景気 |
|
|
|
|
|
|
b.国際的軍事景気による輸出増加 |
|
|
|
|
|
|
③鉱工業生産-D[6 ]の水準に回復(戦前比94%) |
|
|
|
|
|
1951年 |
日米協力体制の強化→新特需→鉱工業生産、戦前の水準へ |
|
|
|
|
|
同 |
政府、D[7 ]産業に国家資金投入 |
|
|
|
|
|
|
①D[8 ・ ]・造船などの産業部門へ積極的に設備投資 |
|
|
|
|
|
|
②経済構造-重化学工業中心へ移行 |
|
|
|
|
|
1952年 |
D[9 ](金本位制による円滑化をはかる国際金融機関)加盟 |
|
|
|
|
|
同 |
E[10 ](世界銀行。復興及経済発展のための資金貸付機関) |
|
|
|
|
|
|
①国際収支の黒字 |
|
|
|
|
|
|
②国際経済における地位向上 |
|
|
|
|
|
1953年 |
A[11 ]協定(休戦成立)→E[12 ](朝鮮復興特別需要) |
|
|
|
|
|
1954年 |
MSA援助協定 |
|
|
|
|
|
1955年 |
*D[13 ]景気(神武以来の好景気) |
|
|
|
|
|
|
①積極的な財政・金融政策 |
|
|
|
|
|
|
②設備投資を中軸とした大型景気 |
|
|
|
|
|
|
③結果 |
|
|
|
|
|
|
a.輸出増大 |
|
|
|
|
|
|
b.日本経済の急成長 |
|
|
|
|
|
1956年 |
経済白書の言葉D「14 」 |
|
|
|
|
|
1957年 |
不況 |
|
3 |
生産の急速な増大の背景 |
|
|
イ |
国内市場 |
|
|
|
① |
労働者の賃金上昇 |
|
|
|
|
a |
若年層を中心とする労働者不足 |
|
|
|
|
b |
労働組合運動の展開 |
|
|
|
② |
農業 |
|
|
|
|
a |
化学肥料・農薬・農業機会の普及→生産力上昇 |
|
|
|
|
|
1960年代 |
消費の停滞→米の生産過剰 |
|
|
|
|
|
1970年 |
生産調整のための減反 |
|
|
|
|
b |
農業協同組合の力によって米価引上げ |
|
|
|
|
c |
農家の農業外所得の増大(第2種兼業農家-1970年50%) |
|
|
|
③ |
所得水準の上昇・消費構造の変化→工業製品の市場を大幅に拡大 |
|
|
ロ |
輸出の拡大 |
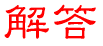 |
|
|
正解数( )問/問題数(14)問=正解率( )%
|