ごあいさつ
第ニ十二回は青木書店
宮澤誠一著『近代日本と「忠臣蔵」幻想』(Ⅵ)
|
「大学生の論文の序論」に終わっているのが残念 期待が大きかっただけに幻想に終わって無念 次作に期待 いう『犯罪』を『美徳』として称賛する人びとの精神と結合することに よって、近世の「赤穂義士」像が誕生」したという。 また「さまざまなテクストを自由に渉猟しながら、時代の状況を鋭く 照らす鏡である『忠臣蔵』を分析することを通して、近代日本の精 神的特質を解明したいと思う」として、ここでは206冊について丹 念に紹介したいる。その労苦に敬意を表したい。 しかし「幻想」という定義が不十分である。過去の書物(「テクスト」) を全て読むことから、大学生の論文は始まる。だから結論部分を楽 しみに読み進んだが、学生の論文の序論にあたる部分で終わって しまっていた。九州大学大学院の大石和世氏も「各論の紹介にとど まり、互いの力関係についての論考が不十分」と指摘している(中央 義士会会報第50号)。学者としての論文を完成させて頂きたい。 終章の最後に、池宮彰一郎氏の『四十七人の刺客』、深作欣二 監督の『忠臣蔵外伝四谷怪談』、岳 真也氏の『吉良の言い分』な どを紹介し、「近代の『忠臣蔵』幻想が、討入の正当性と侍の美意 識を喪失し、人々の心を魅了する呪縛力を失いつつある現在の思 想的状況が端的に写し出されている」と結論付ける。実力者ともな れば過去の作品との違いを強調するために遊びを取り入れるので ある(忠臣蔵新聞第210号)。遊びの要素をもって「心を魅了する呪 縛力を失」lっているという表層的な見方が、とても惜しまれる。 宮澤氏は冒頭で「最近の若い人たちが『忠臣蔵』に興味を抱いて いるとはいえないようである」と曖昧に言うが、是非宮澤氏が勤める 大学の生徒に聞くなどのフィールドワークを重視してもらいたい。 地元赤穂の高校生100人(忠臣蔵新聞第177号から第180号)、 京都の高校生77人(忠臣蔵新聞第第182号から第188号)、滋賀 大の学生22人(忠臣蔵新聞第97号)を参照してもらいたい。 |
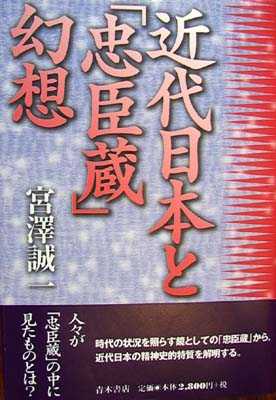 |
| 章 | 番号 | 編著者など | 書名・演劇名 | 発行年 |
| 終 章 現 代 の 忠 臣 蔵 |
159 | GHQ | 法律を無視した個人的復讐を称賛する映画・演劇の禁止通達 | 1945年 |
| 160 | ルース・ベネディクト | 菊と刀 | 1946年 | |
| 161 | 片山伯仙 | 進駐軍も見よ大石の真忠(義士研究叢書) | 1955年 | |
| 162 | 演劇界 | 忠臣蔵特輯 | 1947年 | |
| 163 | 田中英光 | 色欲忠臣蔵(『談話』) | 1948年 | |
| 164 | 片岡千恵蔵 | 赤穂城(東映映画) | 1952年 | |
| 165 | 松田定次 | 赤穂浪士(東映映画) | 1956年 | |
| 166 | 渡辺邦男 | 忠臣蔵(大映映画) | 1958年 | |
| 167 | 稲垣浩 | 忠臣蔵(東宝映画) | 1962年 | |
| 168 | 榊山 潤 | 生きていた吉良上野(小説と読物) | 1950年 | |
| 169 | 村上元三 | 新本忠臣蔵(りべらる) | 1951年 | |
| 170 | 大佛次郎 | 四十八人目の男(読売新聞) | 1951年 | |
| 171 | 舟橋聖一 | 新・忠臣蔵 | 1956年 | |
| 172 | 山田風太郎 | 妖説忠臣蔵 | 1957年 | |
| 173 | 五味康祐 | 薄桜記 | 1959年 | |
| 174 | 尾崎士郎 | 吉良の男 | 1961年 | |
| 175 | 北島正元 | 江戸時代 | 1958年 | |
| 176 | 戸板康二 | 忠臣蔵 | 1957年 | |
| 177 | 小林秀雄 | 忠臣蔵Ⅰ・Ⅱ(文藝春秋) | 1961年 | |
| 178 | 村上元三脚色 | NHK大河ドラマ赤穂浪士(大佛次郎『赤穂浪士』原作) | 1964年 | |
| 179 | 松島栄一 | 忠臣蔵ーその成立と展開 | 1964年 | |
| 180 | 田村栄太郎 | 赤穂浪士 | 1964年 | |
| 181 | 三波春夫 | 大忠臣蔵(長編歌謡浪曲) | 1971年 | |
| 182 | 『仮名手本忠臣蔵』(アメリカのシティー・センターで上演) | 1960年 | ||
| 183 | 福田善之 | しんげき忠臣蔵(俳優座で上演) | 1969年 | |
| 184 | 三船プロ | 大忠臣蔵(現テレビ朝日) | 1971年 | |
| 185 | 南條範夫 | 元禄太平記(NHK大河ドラマ) | 1975年 | |
| 186 | 堺屋太一 | 峠の群像(NHK大河ドラマ) | 1982年 | |
| 187 | 佐藤忠男横光利一 | 忠臣蔵ー意地の系譜 | 1976年 | |
| 188 | 加藤周一 | 日本文学史序説 | 1980年 | |
| 189 | 鶴見俊輔・安田 武 | 忠臣蔵と四谷怪談 | 1983年 | |
| 190 | 尾藤正英 | 元禄時代(日本の歴史) | 1975年 | |
| 191 | 田原嗣郎 | 赤穂四十七士論 | 1978年 | |
| 192 | 渡辺 保 | 忠臣蔵ーもう一つの歴史感覚 | 1981年 | |
| 193 | 丸谷才一 | 忠臣蔵とは何か | 1984年 | |
| 194 | 諏訪春雄 | 聖と俗のドラマツルギー | 1988年 | |
| 195 | モーリス・パンゲ | 自死の日本史 | 1986年 | |
| 196 | モーリス・ベジャール | ザ・カブキ(創作バレエ) | 1986年 | |
| 197 | 森村誠一 | 忠臣蔵上・下 | 1986年 | |
| 198 | 井上ひさし | 不忠臣蔵 | 1985年 | |
| 199 | 小林信彦 | 裏表忠臣蔵 | 1988年 | |
| 200 | 池宮彰一郎 | 四十七人の刺客 | 1992年 | |
| 201 | 深作欣二 | 忠臣蔵外伝四谷怪談(松竹映画) | 1994年 | |
| 202 | 市川 崑 | 四十七人の刺客(東宝映画) | 1994年 | |
| 203 | 湯川裕光 | 瑤泉院 | 1998年 | |
| 204 | 岳 真也 | 吉良の言い分 | 1998年 | |
| 205 | 三枝成彰 | オペラ忠臣蔵 | 1997年 | |
| 206 | 舟橋聖一 | 元禄繚乱(NHK大河ドラマ) | 1999年 |